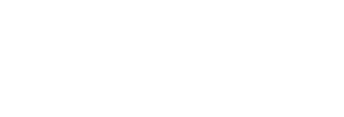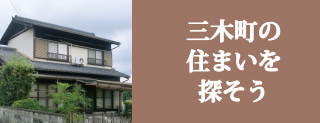- ホーム
- 種を継ぐ 〜蘇る“古(いにしえ)のうどん”〜
種を継ぐ 〜蘇る“古(いにしえ)のうどん”〜

今年、55年ぶりに大阪で開催されている「大阪・関西万博」。世界中から人々が集い、最先端の技術や文化が交錯するこの一大イベント会場の一角に、ひときわ異彩を放つブースが誕生しました。その名も「香川の未来へつなぐ船“せとのかけはし号”」。香川県が誇る食、伝統文化、自然、アートの魅力を余すことなく発信するこのブースは、4月30日から5月3日までの4日間限定でオープンし、国内外から訪れた多くの来場者を魅了しました。
そして、このブースで注目を集めたのが、半世紀以上の時を超えて蘇った“古のうどん”です。使用された小麦は、1970年代に香川県内で広く栽培されていた「農林26号」。かつては香川のうどん文化を支えた存在でしたが、時代の変化とともに「さぬきの夢2000」などの新しい品種に取って代わられ、いつしか姿を消しました。県農業試験場にわずか100gだけが保管されていたこの“幻の小麦”を、「麦縄の里まさご屋SUSURU」店主・真砂泰介さんが家族やスタッフ、地域の仲間たちと共に、数年かけて180kgまで増やすことに成功しました。

真砂さんの挑戦は単なる品種の復刻にとどまりません。地域の大人たちと共に農林26号の栽培に取り組むだけでなく、子どもたちにも麦作りの体験を提供しています。「種を継ぐ」という営みの大切さを、次世代の子どもたちに伝えたい、その強い想いが、地域ぐるみのプロジェクトを動かしています。

白山小学校では、1年生が麦踏み、4年生が麦刈り・種まきなどの作業を体験しています。6月初めには4年生2クラスが麦刈りに挑戦しました。農薬や肥料を一切使わず、環境に配慮した自然農法で育てた麦は、穂が短く背丈が高いため倒れやすいという特徴がありますが、子どもたちは鎌を手に、汗を流しながら丁寧に刈り取りました。「麦の方が刈りやすい」「力が少し必要だけど、工夫すればできる」といった声が聞こえてきました。今年は天候にも恵まれ、約200kgの収穫が見込まれています。
何十年、何百年と受け継がれてきた「種を継ぐ」営みは、安心・安全な食を支えるだけでなく、子どもたちに感謝の気持ちや命の大切さを伝える“生きる力”そのもの。真砂さんは「地域の大人と子どもが関わり合い、顔の見える関係を築くことこそが、幸せなまちづくりの原点」と語ります。
今年の万博では、白山小学校の児童たちが育てた農林26号の小麦が、“古のうどん”として来場者に振る舞われました。自分たちの手で育てた小麦が、世界中から訪れる人々に味わってもらえる。子どもたちにとってかけがえのない経験です。「自分たちが育てた小麦が世界中のみんなに食べてもらえて嬉しい」「香川に来て、ぜひ本場のうどんを食べてほしい」そんな喜びの声が次々と上がりました。
今後は、子どもたちの自由な発想やアイディアを大人たちが形にし、新たな商品やイベントへと発展させていく構想も進行中です。世代を超えて「種」が受け継がれていく。そこには、単なる伝統の継承を超えた、地域全体の幸福度や活力を底上げする力が宿っています。
この小さな種が、子どもたちの夢とともに大きく花開いていくことでしょう。

執筆者
三木町町民Reporter H・Y
夜、窓を開けるとカエルの大合唱。それを子守唄にして眠りにつきます。
まだまだひよっこ三木町民ですが、三木町がもっともっと元気な町になることを願っています。
〒761-0692 香川県木田郡三木町大字氷上310番地
Tel:087-891-3302